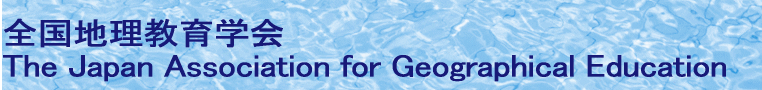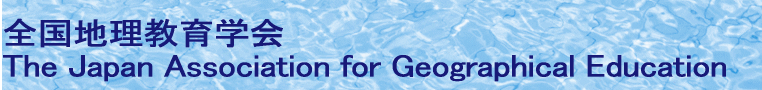期
日
|
2025年 11月 2日(日)
|
会
場 |
畿央大学
〒635-0832
奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2
電話:0745-54-1601
・近鉄大阪線五位堂駅より徒歩15分または五位堂駅よりバスで5分

※大学HP(https://www.kio.ac.jp/guide/campus/access/)より引用
|
主
催 |
全国地理教育学会
全国地理教育学会事務局
〒336-0926
埼玉県さいたま市緑区東浦和6-4-19
浦和明の星女子中学・高等学校 山下 啓
URL:http://www.jageoedu.jp
E-mail:zenchikyo2025@yahoo.co.jp
大会実行委員会
委員長 岡田 良平(畿央大学)、副委員長 齋藤 鮎子(四天王寺大学)、会計 佐藤 浩樹(神戸女子大学)
学生委員
4回生 岡本 茉里、尾前 知香、垣内 智樹、桂 佑弥、紀之定 伶香、田中 瑠惟、玉越 由真、中西 陸人
3回生 今中 涼香、奥本 彩乃、河口 陽、辻本 梨琴、長尾 一輝、西村 咲希、廣石 圭登
学会大会委員会
牛込 裕樹(委員長)、針谷 重輝、松岡 路秀、宮本 静子、山内 洋美、日下部 和宏
E-mail:taikai@jageoedu.jp
|
テ
l
マ
|
地理教育・社会科教育における直接経験(体験)学習、フィールドワーク学習の重要性 |
参
加
費 |
大会参加費:1,500円(会員・非会員)、学生・院生は500円
懇親会費 :5,000円 |
日
程 |
11月1日(土)
9:30 〜 17:00 巡検
11月2日(日)
8:40 受付
9:20 〜 11:50 一般研究発表(10:20〜10:55は休憩、10:30〜10:45はポスター発表)
12:00 〜 12:45 評議員会(12:30〜12:45 ポスター発表)
13:00 〜 15:35 シンポジウム
15:50 〜 16:20 総会
16:40 〜 18:10 懇親会(大学食堂 カトレア)
|
一
般
研
究
発
表
|
■一般研究発表(第1会場 P201教室)
(発表時間、各15分、質疑4分、計19分)
座長101-103:伊藤 裕康(文教大学)
101 9:20-9:39
河野 富男(香川県宇多津町立宇多津北小学校)
体験と、繋ぎ地域の地理的感覚を培う小学校社会科授業
−第4学年「水はどこから」の授業実践の場合−
102 9:40-9:59
佐藤 浩樹(神戸女子大学)
平成29年版小学校社会科学習指導要領における内容の枠組みの課題
−地理的概念を矮小化した地理的見方の問題点−
103 10:00-10:19
久保 哲成(神戸学院大学・非)
景観写真の読み取りを促すフレームワークの検討
−認識論的二元論と認識論的実在論との立場から−
休憩(10:20-10:55 この間、10:30-10:45、ポスター発表)
座長104-106:横山 満(全国地理教育学会副会長)
104 10:55-11:14
飯島 善章(洗足学園中学高等学校)
VR体験を通じたバーチャル・フィールドワーク
−地理的・歴史的な認識に対する効果と課題−
105 11:15-11:34
小関 勇次(清和大学)
50分・90分で完結する地理のactivity
106 11:35-11:54
齋藤 鮎子(四天王寺大学文学部)
新課程地理領域科目におけるエデュテイメントの可能性
−桃太郎電鉄を用いた授業の実践−
■一般研究発表(第2会場 P202教室)
(発表時間、各15分、質疑4分、計19分)
座長201-203:今井 英文(山陽学園大学・非常勤講師)
201 9:20-9:39
菊地 達夫(北翔大学短大部)
地誌学における世界地誌学習の実践と成果
202 9:40-9:59
西岡 尚也(大阪商業大学公共学部)
アフリカ地誌を教養科目としてどう教えるか
−大学生へのアンケートからの考察−
203 10:00-10:19
大島 悟(島根大学教育学部附属義務教育学校)
竹島問題の平和的解決に向けた対話に着目した指導についての研究
−中学校社会科歴史的分野小単元「日韓国交正常化交渉と竹島問題」の再提案−
休憩(10:20-10:55 この間、10:30-10:45、ポスター発表)
座長204-206:鈴木 正行(香川大学)
204 10:55-11:14
永田 成文(広島修道大学)
シビックプライドを育成する観光の視点を取り入れたESD授業の構想
205 11:15-11:34
山口 幸男(群馬大学名誉教授)
大正期の3書における地理教育論と時代認識
−牧口、西田、齋藤の3書について−
206 11:35-11:54
野間 晴雄(関西大学東西学術研究所・客員研究員)
浮田典良の地理教育論
−明晰な段取りと情愛の50年
|
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
|
テーマ:地理教育・社会科教育における直接経験(体験)学習、フィールドワーク学習の重要性
趣旨
AIやICT教育、個別最適な学習と協働的な学習、教員の働き方改革など、教育を取り巻く環境が劇的に変化している。特に、AI、ICT、バーチャル空間は、地理教育・社会科教育が伝統的に重視してきた直接経験(体験)学習、フィールドワーク学習の価値を弱体化させる可能性がある。そこで、今一度、直接経験(体験)学習、フィールドワーク学習の持つ教育的重要性を再確認することが必要であると思われる。そのためには、直接経験(体験)学習、フィールドワーク学習を単にやりっぱなしで終わるのではなく、それらが地域認識・社会認識・人間形成にとって如何に意味あるものであるか、その価値・重要性を具体的理論的に検証・評価することが肝要となる。このことは、次期学習指導要領に対する提言としても意義を持つものと思われる。
発表者
①岡田 良平(畿央大学)
②七里 広志(兵庫教育大学連合大学院連合学校教育学研究科・草津市立老上中学校)
③辰己 勝(奈良大学・非)
コメンテーター
野間 晴雄(関西大学名誉教授)
オーガナイザー
佐藤 浩樹(神戸女子大学)
岡田 良平(畿央大学)
牛込 裕樹(大妻中野中学校・高等学校)
|
ポ
ス
タ
l
発
表
|
岡田ゼミ学生(10:30〜10:45、12:30〜12:45)
|
巡
検
|
テーマ
奈良中部・宗教都市天理と環濠集落今井町
実施
畿央大学岡田ゼミ
日程
2025年11月1日(土)9:30〜17:00頃
※雨天決行。交通渋滞によって予定時刻が遅れる可能性があります。
集合
近鉄天理線「二階堂」駅に9:30集合(徒歩15分程度)
体験会場は「平宗 便利館」になります。直接お越しになる場合は9:45集合
※時間厳守でお願いします(10時から体験開始となります)。
コース
9:30 近鉄天理線二階堂駅集合 → 9:45 平宗便利館集合 → 10:00 柿の葉寿司づくり体験(体験は11:30まで。一時解散。店舗にて昼食を食べることもできるようしています) → 12:30 JR天理駅団体待合室集合 → 天理本通り商店街 → 13:30 天理大学附属参考館(14:30まで) → 天理本通り商店街 → 15:08JR天理駅(万葉まほろば線) → 15:30畝傍 → 16:00今井町(今井町まちなみ交流センター等見学:各施設17:00閉館)・解散
参加費
無料
柿の葉寿司体験(12個入り2,750円)
天理大学附属参考館入館料500円(20名以上であれば団体割引になります)
現地払いです。お釣りの無いようご協力をお願いします。
申込先
電子メール(r.okada@kio.ac.jp)にて、以下①②をご連絡ください。
①参加者氏名
②参加形態(全日・午前のみ・午後のみの3形態から選択)
午後から参加の方は12:30 JR天理駅団体待合室集合もしくは、13:30天理大学附属参考館に集合してください。
※天理参考館は非常に大きな博物館ですが、見学時間が短くなっているため一足先に入館をご希望される方(JR天理駅団体待合室集合をしない方)は予め岡田までご連絡下さい。
締切:2025年10月15日(水)必着
ご都合により柿の葉寿司づくりをキャンセルされる場合は10月25日までにご連絡下さい。
|
プ
ロ
グ
ラ
ム
|
Word形式 PDF形式 |
大会参加・一般研究発表・懇親会の申込み方法
(1)大会参加、一般研究発表、懇親会の申込み
次の①か②の方法でお申込みください。
①ホームページより参加申し込み用紙をダウンロードし必要事項を入力して電子メールで送る。
※注意 電子メールの件名に「大会参加申込み」もしくは「大会参加及び発表申込み」と記入願います。
②参加申込み用紙に必要事項を記入して、大会事務局へ郵送、ファックスで送る。
(申込み先は申込み用紙の下部に記載してあります)
(2)一般研究発表の申込み、及び要旨集原稿期限
発表申込締切日:8月20日(水) 必着
要旨集原稿締切日:9月29日(月) 必着
発表希望者はホームページより発表要旨集作成要領をダウンロードし、その要領にしたがって発表要旨を作成し、電子メールか郵送で送付してください。
(詳細は作成要領をご覧ください。)
なお、第13回大会より作成要領が変更になっておりますのでご注意ください。
●申込み先:申込用紙(4ページ)をご覧ください。
(3)非会員
参加申込用紙をお送りいただくか、当日、直接会場にお越しください。
問合せ先
大会参加及び発表申込:大会専用メールアドレス taikai@jageoedu.jp
大会全般:大会委員長 牛込 裕樹 090-1846-3359、taikai@jageoedu.jp
巡検申込み:大会実行委員長 岡田 良平 r.okada@kio.ac.jp
|
大会要項
兼申込用紙 |
Word形式 PDF形式 |
大会発表
要旨集
作成要領 |
Word形式 PDF形式 |